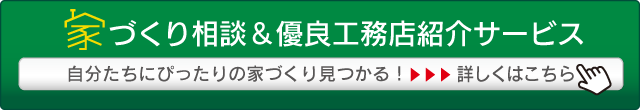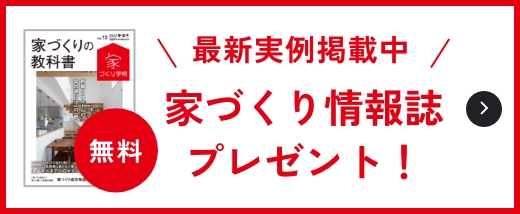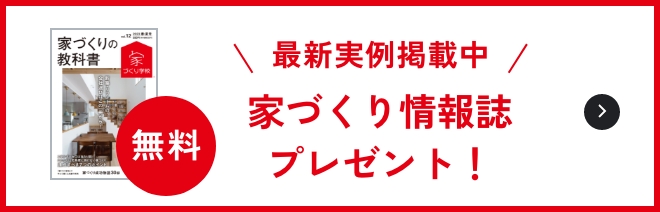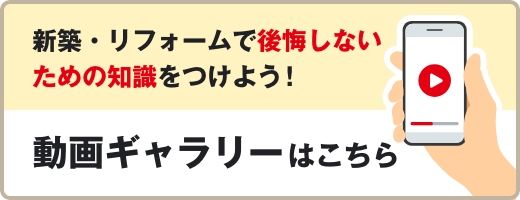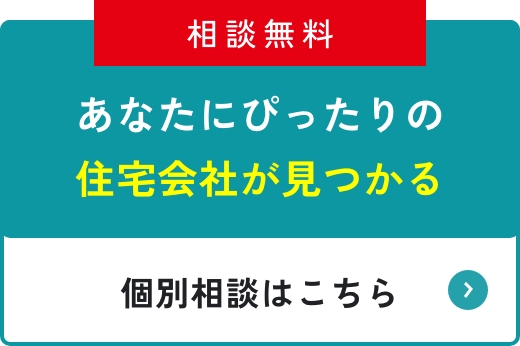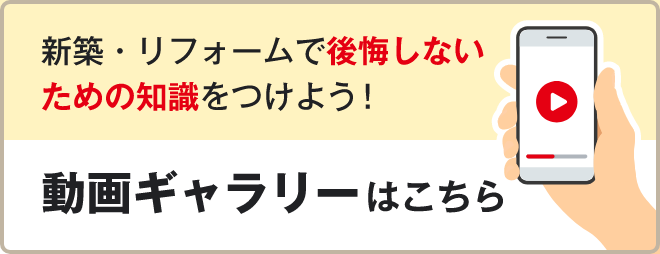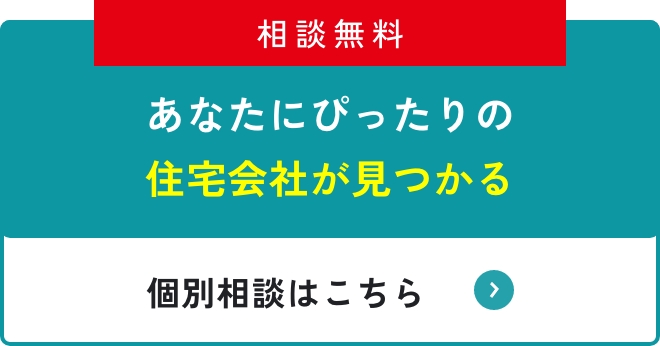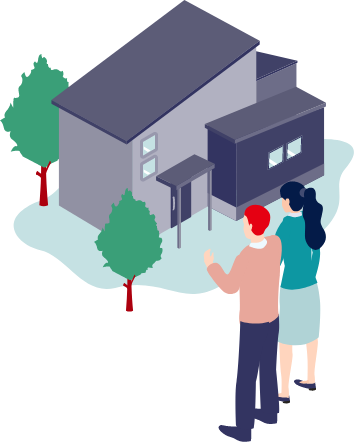水害に備える家づくり
2023.10.25
2018.11.15

年々増加傾向にある日本の自然災害。近年では、令和元年の西日本豪雨や令和2年の熊本豪雨など、水害が甚大な被害をもたらしています。西日本豪雨では20.663棟が全半壊等、29.766棟が家屋浸水の被害を受けました。(国土交通省調べ)
この記事ではこれから家を建てる方はもちろんのこと、これまで対策していなかったという方にも、ぜひ水害に備えて知っておいていただきたいことをまとめました。
ハザードマップの確認


まず重要なのが「ハザードマップ」の確認です。ハザードマップとは、自然災害が起こった場合、その被害がどの程度まで及ぶ可能性があるのか?避難経路は?避難場所は?などの情報を地図にまとめたものです。
2020年8月から不動産の取引時に水害ハザードマップを用いた水害リスクの説明を行うことが義務化されました。予めそういった地域の災害に関する情報が頭に入っていれば、リスクを踏まえた上で家を建てることができますし、実際に災害に遭ったとしても、被害を最小限に抑えることができるかもしれません。
ぜひ、国土交通省ハザードマップポータルサイトから、該当地域のハザードマップを探してみてください。
<家づくり学校周辺地域のハザードマップ情報はコチラ>
家づくりにおける水害対策は?

水害が発生したとき、家屋の被害が大きくなる原因が「浸水」です。家を建てる際にはこの「浸水」をいかに防ぐのかが重要です。浸水には床上浸水と床下浸水の2種類があります。住宅の上まで水がきたら「床上浸水」。床上まで浸水せずとも、住宅の基礎の部分が浸水すると「床下浸水」になります。
「床上浸水」方が、家屋へのダメージは大きいです。
「床上浸水」すると、汚泥が床の上だけでなく床下にも流れ込み、カビや細菌が繁殖しやすい状態になります。そうなると汚泥を片付けるだけでなく、洗浄や消毒なども必要になるため、床上浸水を防げるかどうかでその後の処理のしやすさや手間が変わってくるのです。また、「床上浸水」では家電が水没して使えなくなるケースも。そうなると買い替えの費用も必要となります。
では、「浸水」を防ぐためにはどんなことができるのかチェックしていきましょう。
床を高くする
建物の床を高くすることで、床上浸水の可能性が減らせます。
特に海沿いや川沿いにお家を建てる方は、「高床式住宅」を選ぶ方が増えています。「高床式住宅」とは、建物の1階部分を駐車場などにし、2階に居住空間を設けた住まいのことです。
ハザードマップで想定される水位よりも床の高い高床式の住まいにしておくことで、浸水による被害を最小限にすることができます。
地盤を高くする

水害被害を抑えるためには、「地盤」の強度についても知っておく必要があります。検討している土地がある場合は、近隣に建っている住宅がどうしているかを見るのも参考になります。長くその地域に住んでいる住民と話ができれば、用水路が増水しやすいとか〇〇年前に床下浸水したとか、こまかな地域情報も得られるでしょう。
また、土地の地名で推測することもできます。例えば、「海」や「池」「河」のようにサンズイのはいった漢字が使われている地名は、かつて湿地帯であった可能性があります。地名にはその土地の歴史が記されていることが多いため、こういったポイントも押さえたうえで、土地を選ぶことが大切です。
また、周辺の環境によっては、盛り土を行い、敷地全体を高くします。水は高所から低所へ流れるという性質があるため、地盤を高くすることで浸水のリスクを減らすことができます。
ただ、軟弱な地盤の場所では不向きなため、必ず土地の性質や周囲の環境を踏まえて、土地の購入や建築を検討することが必要です。
防水性の高い壁で家を囲む
特に駐車場が道路より少し低い位置にあったり、地下に部屋があったり、水が流れ込みやすい造りになっている場合に必要な対策です。防水性の高い外壁を設けることで、建物への浸水被害を低減することができます。
建物を防水性の高い建材で囲む
水害の場合に限らず、風雨や紫外線による経年劣化を遅らせる意味でもメリットがあり、家を長期的に維持する上でも効果的な対策です。
火災保険(水災)への加入

水害に遭ってしまった後の負担を軽くしてくれるのが「保険」です。火災保険に「水災」をつけていれば、補償されるケースもあります。
火災保険はこの「水災」を外すと安くなるため、近くに海や川がないというエリアでは意外と外している方が多いです。是非この機会に、火災保険に入っているのか?そしてその火災保険には水災補償がついているのか?を、チェックしてみてください。
そもそも、火災保険(水災)では、どのような場合に補償されるのでしょうか?
補償されるケース
①洪水
台風、暴風雨などにより河川の水量が急激に増加して発生した洪水や、融雪による洪水での被害を補償。また、ゲリラ豪雨などにより排水が追い付かず床上浸水となった場合も補償してくれます。
②高潮
台風や発達した低気圧などにより海水面が普段より著しく上昇することにより、防波堤などを超えて海水が流れ込み、浸水被害に遭った場合に補償してくれます。
③土砂崩れ
大雨や集中豪雨などにより、山の斜面や崖などの土砂が崩れ落ちる被害を補償してくれます。川底の土砂や泥が一気に流される土石流も補償の対象です。
水災補償の支払要件
どういう状況になると、保険金が支払われるのでしょうか。
- 再調達価額の30%以上の損害
- 床上浸水または地盤面から45cmを超えて浸水
再調達価額というのは、保険の目的(建物や家財)と同等のものを新しく建築したり購入したりする際に必要となる金額のこと。保険会社によって「再取得価額」や「新価」、「保険価額」など呼び名が異なることがあります。
損害保険金として支払われる金額は、損害額から免責金額を差し引いた残りの金額です。免責金額とは、保険会社が保険金を支払う責任がない金額で、契約時にあらかじめ決めた自己負担額のことです。
被災時にやるべき事~写真で記録を残す~
火災保険(水災)に加入している場合、被災してしまったときにやっておかなければならないことがあります。それは「写真を撮ること」。被害状況が分かるよう、必ず片付ける前に必ず写真を撮るようにしましょう。
写真を撮るときに気をつけていただきたいのが、下記の5点です。
①写真は一枚だけでなく、4方向から撮って建物全体の損傷が分かるようにしましょう。
②浸水した位置が分かるようにメジャーと一緒に写しましょう。もし、メジャーがなければ、人に立ってもらって一緒に写すとおおよその深さが分かります。
③壁、畳、床が水を吸って膨れていませんか?膨れている場合は、写真に撮っておきましょう。
④台所、トイレ、風呂などが浸水していないかを確認して写真に撮っておきましょう。
⑤柱の傾きを撮っておきましょう。
水災補償が支払われないケース
水害と同じようにとらえがちですが、水漏れや地震による土砂災害・津波などは水災補償の対象ではなく「地震保険」の補償対象です。
また、保険法により、保険金の請求期限が3年と決められているため、災害が起こってから保険請求までに3年以上が経ったケースは保険金が支払われない可能性があります。被害に遭った場合速やかに保険会社に連絡し、請求しましょう。また、保険会社によっては、保険法とは異なる請求期限を設けている場合もあります。あらかじめ、ご自身の加入している保険の補償内容について確認しておくことが大切です。
もし、水災被害に遭ってしまった際は、まずはお住まいの自治体のホームページよりどんな支援が受けられるか確認してみてください。
あらゆる方面から備えておこう

いかがでしたか?
今回は「水害」に備えるために、特に住居に関して知っておいていただきたいことを中心にまとめました。
浸水対策を施すための具体的な方法などは、専門家の指示を仰ぐのが一番。でもどういう対策をとればいいのかを知っていないと、納得のいく家づくりはできません。まずはハザードマップを確認し、どのような備えをすべきなのか考えてみましょう。
水害だけでなく、地震やその他の自然災害についても、疑問があればぜひ家づくり学校でご相談ください。家づくりをする上でどのような点に気をつければいいか、アドバイザーが丁寧にレクチャーします。→無料相談の詳細についてはこちらから。
地震に強い家づくりをするためのポイントはこちらの記事でご紹介しています。→地震に強い家って?地震に備えた家づくりをしよう