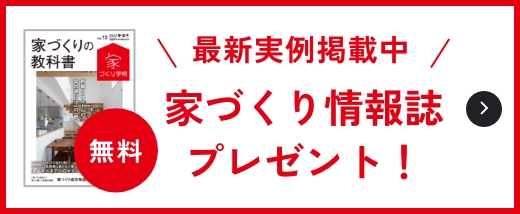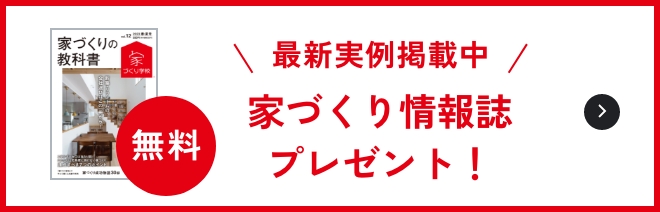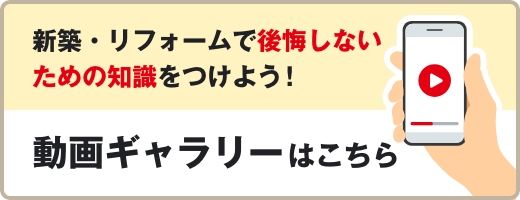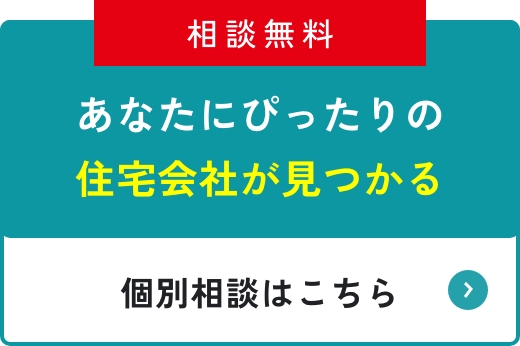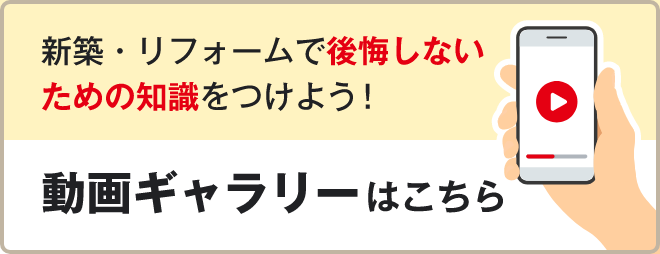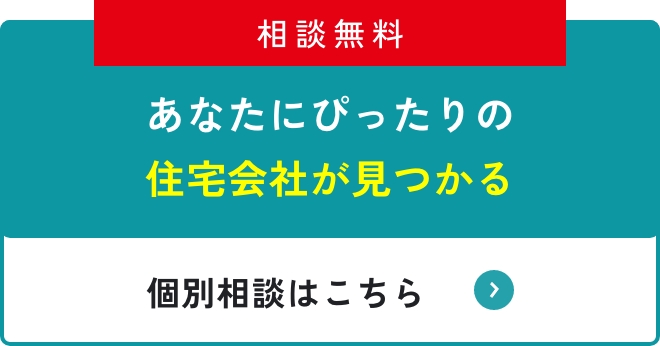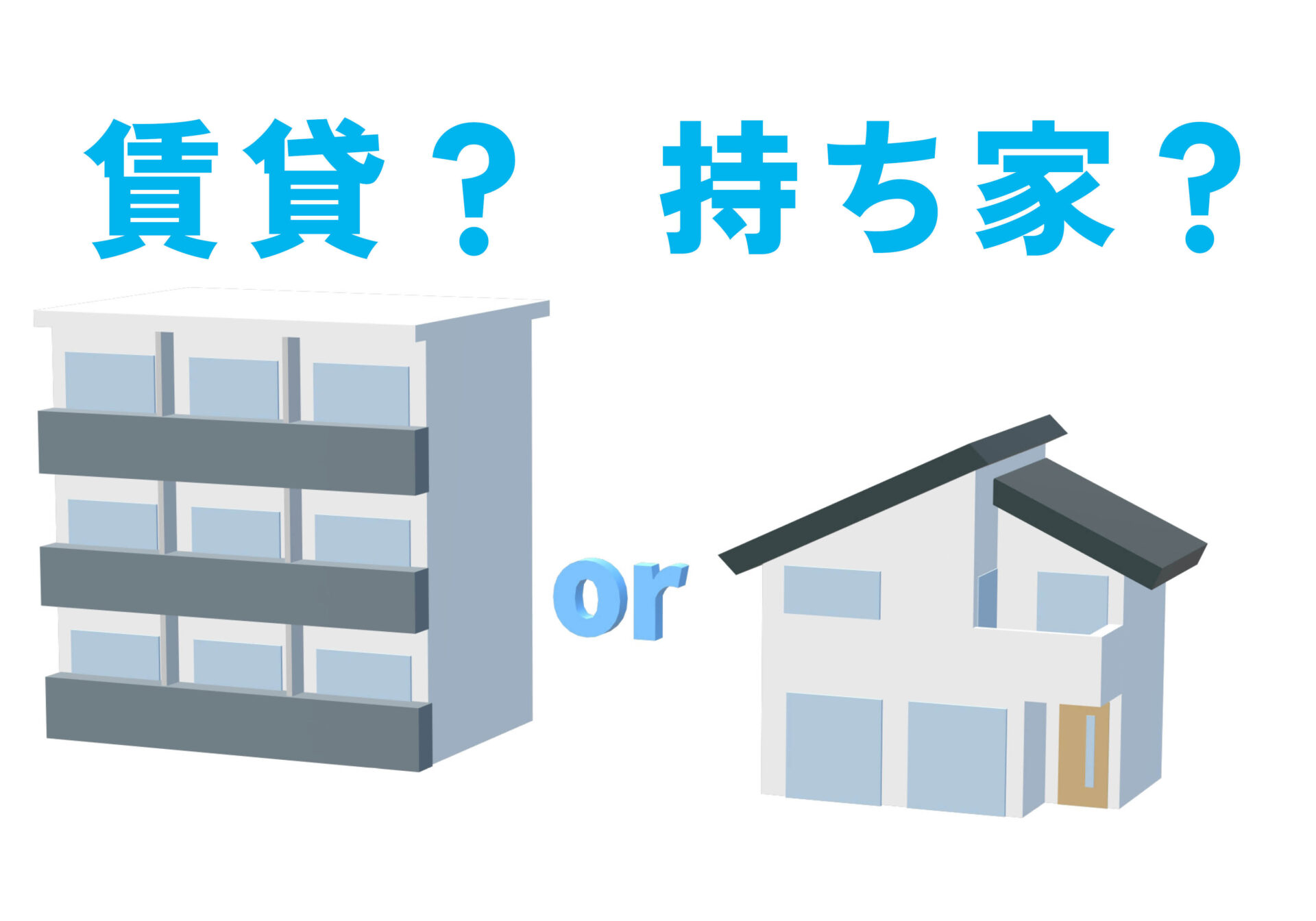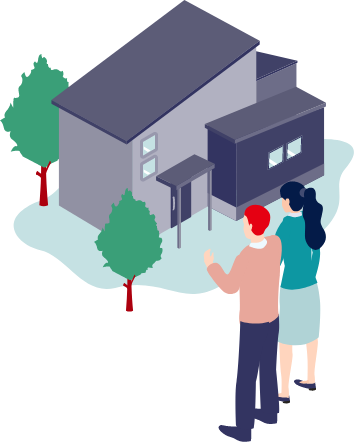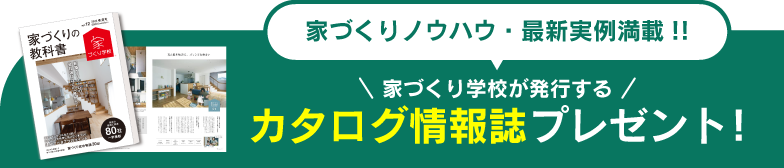50代からの住宅購入資金はどう考える?

最近、50代のご家族の家づくり相談が増えてきました。50代で初めて家づくりをされる方からの質問で多いのは次の2つです。
「この年齢でも住宅ローンは組めますか?」
「家を購入しても定年後の生活は大丈夫でしょうか?」
多くの方が、住宅ローンを組むことへの不安と老後資金との両立という心配事を抱えて家づくりを考えていらっしゃるということなのでしょう。
50代からの住宅購入はこれからの人生を豊かにするための投資です。若い世代とは異なり、老後を見据えたより慎重な資金計画が不可欠となります。ここでは、資金計画を立てるうえで特に留意すべき点を解説します。
この記事を監修した人

家づくり学校アドバイザー / 2級FP技能士・住宅ローンアドバイザー
今井 園美
子どもの教育資金で苦労した経験からファイナンシャルプランナーの資格を取得。家づくり学校ではアドバイザーとして家づくり全般のサポートをするのはもちろん、専門知識でお金や住宅ローンの悩みも解決している。
FP監修のマネーコラムはこちら >>
「この年齢でも住宅ローンは組めますか?」
50代でも住宅ローンを組むことは十分に可能です。ただし、50代ならではの注意点がいくつかあります。
長期の住宅ローンが組めない
一般的に住宅ローンの完済年齢は「80歳」に設定されていることが多いため、50代以降の場合、返済期間は最長30年となります。
※最近は完済年齢が「85歳」まで、という金融機関が出てきました。その場合は最長35年までとなります。
最近の傾向として返済期間が40年間、50年間と超長期の住宅ローンもありますが、いずれも完済年齢は「80歳」までとなっていることが多く、50代では40年、50年といった超長期の住宅ローンを組むことはできません。
長期の住宅ローンが組めなかった場合、次のような注意点があります
借入できる金額が少なくなる
(例)
50歳 年収650万円の場合
試算条件:金利2.0% 元利均等返済
返済期間:30年間
借入できる金額→5,120万円
一般的な返済期間35年間であれば借入できる金額は5,720万円となりますので、返済期間が短くなることで借入できる金額が少なくなることがわかります。
定年退職を迎える65歳までに完済したいと考えた場合はどうなるでしょうか?
返済期間:15年間
借入できる金額→2,940万円
借入期間が短くなると借入できる金額が少なくなります。そうなってくると予算に足りない分をカバーするために自己資金をどこまで準備するか?が重要になってきます。
毎月の返済額の負担が大きくなる
(例)
50歳 借入額3,000万円の場合
金利:2.0%
元利均等返済
返済期間:30年間の場合
毎月返済額→110,885円
返済期間:35年間の場合
毎月返済額は、99,378円
定年退職時65歳までに完済の場合
返済期間:15年間
毎月返済額→193,053円
返済期間が短くなることで毎月の返済額が増えて、家計のへの負担も大きくなっていきます。
完済年齢80歳の住宅ローンの場合、契約時の年齢が50歳であれば返済期間は最大で30年。そこから51歳、52歳と年齢を重ねていくと、返済期間は29年、28年と1年単位で短くなっていきます。返済期間が短くなっていくことによって借入額や毎月返済額への影響も大きくなります。
50代からの家づくりには、借入額と自己資金のバランスを慎重に考えることが重要になってきます。
団体信用生命保険(通称:団信)に注意
多くの金融機関の住宅ローンでは、団信への加入が必須要件となっています。
団体信用生命保険(通称:団信)とは?
住宅ローンの契約者が、死亡または所定の高度障害状態となった場合、ローン残高相当分の保険金が支払われ、住宅ローンが完済される生命保険です。
通常、団信の保険料は住宅ローンの金利に含まれており、契約者が別途負担する必要はありません。
団信の申込時には、契約者の健康状態の告知および引受生命保険会社による加入審査があります。
50代ともなると持病や病歴があって健康状態に不安があるという方もいらっしゃると思います。
持病や病歴によって団信に加入することができなくなると、その結果、住宅ローンを組むことができなくなってしまう可能性も考えられます。そういった持病がある人などを対象に引受基準を緩やかにした「ワイド団信」もあります。その場合、基本的に保険料は金利に上乗せとなります。
住宅ローンの事前審査の段階で、団信の加入審査を受けることができる金融機関もありますので、不安がある方は事前に金融機関に相談される方が安心ではないでしょうか?
疾病保障特約付き団信に注意
最近では、がん(所定の悪性新生物)と診断確定されたらローン残高が0円となる「がん保障特約付団信(がん団信)」などのように、金利に上乗せして保険料を支払うことで保障内容を手厚くできる団信も増えてきました。
通常の団信に加えて、がん団信、3大疾病団信、5大疾病団信や8大疾病団信などを用意している金融機関もあります。こういった疾病特約付団信の場合、加入年齢が50歳以下などに限定されていることが多いため、加入条件をしっかり確認して検討しましょう。
「家を購入しても定年後の生活は大丈夫でしょうか?」
「家を建てたいけど、定年後の生活が不安…」そんな思いから、家づくりに一歩踏み出せない50代の方も少なくないと思います。
50代からの住宅購入は人生の大きな決断であるため、定年後の生活や収入の変動を考慮した慎重な計画が不可欠です。
老後資金はいくら必要?
住宅ローンを組んでも退職金で繰上返済すれば大丈夫、と考えていませんか?退職金は老後の大切な生活資金です。住宅購入資金として使いすぎると老後の生活が立ち行かなくなることも・・・
住宅購入の資金計画を立てる前に、まず老後資金がいくら必要なのかを把握しましょう。
老後資金といえば、2019年に金融庁が公表した報告書がきっかけとなり「老後2,000万円問題」が注目を集めました。その影響で「老後資金って2,000万円必要なのですか?」という質問を多くいただきます。
老後資金は、定年後の「収入:年金」で「支出:生活費」をどの程度まかなえるのか?不足分はいくらになるのか?具体的に計算する必要があります。
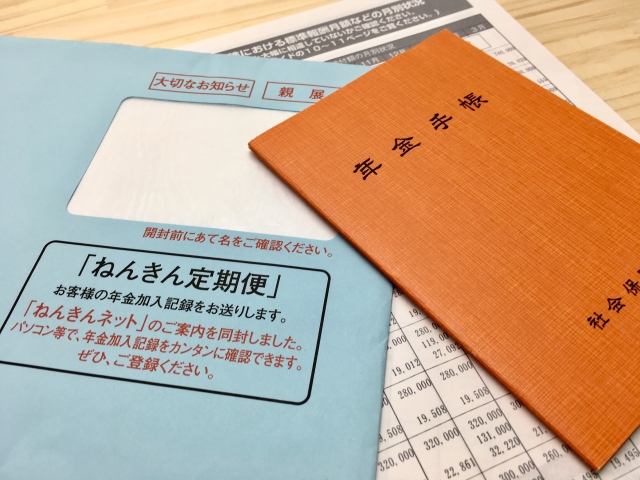
【収入】公的年金を見積もる
2023年度(令和5年度)厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると
65歳からもらえる平均年金月額は以下の通りです。
共働き夫婦世帯:280,963円
夫(会社員)妻(主婦)世帯:227,184円
【支出】生活費を見積もる
総務省「家計調査報告」によると
2024年(令和6年)の二人以上の世帯の消費支出は1カ月平均300,243円
※「消費支出」とは、日常の生活を営むに当たり必要な商品やサービスを購入して実際に支払った金額のこと。食料品、住居、光熱費、被服費、交通費、教育費、娯楽費など、生活に必要なあらゆる支出が含まれています。
前年に比べて名目2.1%の増加となっていますが、物価変動(3.2%)の影響を除いた実質では1.1%の減少となっています。このところの物価上昇の影響を大きく受けているようです。
とはいえ、あくまでも一般的な平均値。実際の生活費はご家族のライフスタイルやご家族状況によって異なります。
【収支】老後に不足する金額は?
月の平均支出額を30万円で考えた場合
共働き世帯の場合、毎月の不足分は約2万円
85歳までの不足額⇢▲480万円
90歳までの不足額⇢▲600万円
夫(会社員)妻(主婦)世帯の場合、毎月の不足分は約7.3万円
85歳までの不足額⇢▲1,752万円
90歳までの不足額⇢▲2,190万円
ただし、この金額はあくまでも今回のモデルケースに基づいた試算結果であって、誰にでも当てはまる訳ではありません。ご家庭ごとのライフスタイルやご家族状況によって異なってきます。
では、自分たち家族の場合はどうなの?まだ先の話とはいえ、自分たちの老後資金がいくら必要なのか?せめて目安額だけでもわかれば、、と考えてしまいますよね。自分たちのケースはどうなのか?試算してみましょう!
自分の公的年金を把握する
公的年金は、老後の生活を支えるベースとなるものです。どのくらいもらえるのか?目安額を知っておくと計画が立てやすくなります。次の方法で目安額を試算できます。
【確認方法】
★日本年金機構が発行する「ねんきん定期便」
毎年誕生月に郵送されてきます。「ねんきん定期便」の二次元コードをスキャンして、将来受け取る年金額の試算もできます。
厚生労働省「公的年金シミュレーター」
https://nenkin-shisan.mhlw.go.jp/
※ねんきん定期便に記載の二次元コードからアクセスできます。
★日本年金機構の「ねんきんネット」
ログインすることで将来受け取る老齢年金の見込額を試算することができます。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
※マイナポータルを経由してログインするとかんたんにできます。
自分たちの生活費を把握する
「家計簿をつけていないから支出がどのくらいかがわからない」という方もいらっしゃるでしょう。まずはかんたんな方法で年間の支出額を出してみましょう。
①直近一年間の手取り収入の合計額を出す
②直近一年間の貯蓄の増減額を出す
①-②が一年間支出合計額となります。要は、1年間のすべての収入から、1年間で貯蓄できた金額を差し引いた金額は、すべて「支出」とみなすということです。この場合の貯蓄の中には、iDeCoやNISAなどの資産運用の資金や勤務先の財形貯蓄なども含まれます。
(例)
①一年間の手取り収入:640万円
②一年間の貯蓄増減額:+180万円
↓
640万円-180万円=460万円(←年間の支出額)
月の平均では、383,333円となります。
えっ、ここまで生活費を使っていない、と思われたかもしれません。ただ、この金額の中には毎月の生活費のほかに冠婚葬祭費や家電の購入費など突発的に必要となった支出もすべて含まれます。
ここまででわかるのは「現在の生活費」です。定年後、年金生活になったら質素倹約に努めるからここまで生活費は必要ないという方もいらっしゃることでしょう。であれば、節約分を想定した生活費で算出されてもよいと思います。
「公的年金」の概算額と「自分たちの生活費」を比較し、不足する金額がどれくらいになるかを把握しましょう。
その他の支出
老後の生活を安心して送るためには、毎日の生活費に加えて「特別な支出」に備える必要があります。
・医療・介護費用
・住宅関連費用
・車の買い替え費用
・葬儀関連費用
・子どもや孫への支援金
これらの費用は、個人のライフスタイルや健康状態によって大きく変動します。老後の生活を具体的にイメージし、自分に合った資金計画を立てていくことが大切です。
老後資金を確保した上で、残りの資金を住宅購入に充てる、という考え方が重要です。
購入後にかかってくる費用は?
住宅を所有すると、住宅ローンの返済以外にもさまざまな費用が発生します。これらの費用が老後資金に影響してくることも考えられます。購入後も継続してかかるこれらの費用を事前に把握しておくことは、無理のない資金計画を立てる上で非常に重要なポイントです。
税金
住宅を所有している間は、毎年税金がかかります。
【固定資産税】
毎年1月1日時点の土地と建物の所有者に対して課税される税金
固定資産の所在する市町村が課税する
【都市計画税】
市街化区域内に土地や建物を所有している場合に、固定資産税と合わせて課税される税金
都市の開発のために使うことを目的とした税金であるため、市街化を抑制している市街化調整区域や都市計画が進んでいない都市計画区域外では課税されない
一般的に、固定資産税と都市計画税は一緒に納税します。
★金額の目安
税額は土地と建物の評価額によって決まります。
土地に関しては「住宅用地に対する課税標準額の特例」が、新築住宅の建物部分についても一定の要件を満たすことで固定資産税が一定期間(一般の住宅で3年間、長期優良住宅で5年間など)2分の1に減額される特例があります。
税額は条件によって異なるため一概にはいえませんが、目安額としては年間10万円~15万円程度、軽減措置がなくなって以降は年間15万円~20万円程度が平均的な相場とされています。
保険料
万が一の災害に備えるための保険料も、継続的に発生する費用です。
【火災保険】
火災や落雷、風水害、ひょう災、雪災などによる損害を補償する保険
多くの金融機関では、住宅ローン契約の条件として加入を義務付けています。
【地震保険】
火災保険では補償されない、地震や噴火、津波による損害を補償する保険
火災保険とセットで加入するのが一般的です。
★金額の目安
建物の構造や所在地、補償内容によって異なりますが、年間で数万円程度が一般的です
維持管理・修繕費用
家を長く、安全に保つためには、定期的なメンテナンスや修繕が必要です。一戸建て住宅の場合、マンションのように修繕積立金の制度がないため計画的に自分で費用を積み立てる必要があります。
【定期的な費用】
シロアリ対策:5年~10年ごと 10万円~20万円
給湯器の交換:10年〜15年ごと 20万円〜40万円
【築10年~20年】60万円~150万円
外壁の再塗装(サイディングの場合)
屋根の補修・再塗装
ベランダの防水工事
【20年以上】300万円~700万円
外壁の張り替え・重ね張り
屋根材の葺き替え
水回り設備(キッチン、浴室、トイレ)の交換
内装(壁紙、床材)のリフォーム
一般的な木造住宅の新築から30年程度までのメンテナンス費用は、総額400万円~1,000万円以上が目安とされています。
塗り替え不要の外壁や、耐久性の高い屋根材など、メンテナンスフリーの建材を選ぶことで長期的なメンテナンス費用を抑えることができると言われています。そうすれば老後の負担の軽減にも繋がります。

家族の状況で変わる資金計画の考え方
「50代からの家づくり」と一言で言っても、ご家庭の状況は様々です。お子さんが独立しているご夫婦、まだ小さなお子さんがいるご家庭、そして親御さんとの同居を考えているご家庭。それぞれに資金計画の考え方も異なります。
お子さんが独立しているご夫婦
お子さんが巣立った後の家づくりは、夫婦二人の「セカンドライフ」をどう豊かにするか、という視点が中心になります。
現金購入も視野に
住宅ローンを組むより、退職金や貯蓄で現金購入できるなら、それに越したことはありません。住宅ローンを利用した場合、利息のほかに、事務手数料や保証料、抵当権の設定費用などが必要となってきます。これらは現金購入であれば不要な支出です。
ローンの期間を短く
全額現金購入が難しければ、頭金を多く入れることで借入額を減らし、返済期間を短く設定しましょう。定年後の年金収入や再雇用による収入減を見据え、無理のない返済計画を立てることが重要です。
小さなお子さんがいるご家庭
50代で小さなお子さんがいるご家庭は、まだまだ子育てが中心となります。お子さんの教育費と家の建築費用を同時に考える必要があります。
ローン期間の長期にする
返済期間を長く取ることで、毎月の負担額を減らすことができます。ただし、定年後の収入減を見据えた返済計画は不可欠です。
教育費と住宅ローンのバランス
今後かかる教育費(大学進学費用など)と、住宅ローンの返済が重なる時期があることを忘れてはいけません。教育費と住宅購入費、どちらにどのくらいお金をかけるか、ライフプラン全体を考慮してバランスを取ることが大切になってきます。
親との同居を考えるご家庭
親御さんとの同居を考える場合は、二世帯住宅や三世代住宅の選択肢が出てきます。
親からの援助資金
親からの資金援助があれば、住宅ローンの借入額を大幅に減らすことができます。ただし、贈与税や相続税の問題も出てくるため、事前に専門家に相談しましょう。
親子リレーローン
親子で収入を合算してローンを組み、二世代にわたってローンを返済していく「親子リレーローン」も選択肢の一つです。これにより、借入期間を長く設定し、月々の返済額を抑えることができます。親と子、ともに借金をしていることになりますので、返済期間中に別のローンを組もうと思っても新規の借入が難しいこともあるため慎重な判断が必要です。
単身で家づくりを考える方
ひとりの生活だからこそ、定年後は、より快適で安心な住まいにしたいという想いで家づくりを考える方もいらっしゃいます。
老後資金の確保が最優先
健康不安は、一人暮らしの方が最も懸念する点の一つです。万が一の病気や失業、急な出費に備えるための「生活防衛費」は手元に残しておく必要があります。固定資産税、メンテナンス費用、光熱費なども含めた、定年後の生活費を具体的にシミュレーションしておきましょう。
貯金計画と返済計画を同時に考える
病気や失業で収入が途絶えると、家計が破綻するリスクが直接的に返済に影響します。住宅ローン返済と並行して、老後資金や万一のための生活防衛資金を確保する計画を立てておきましょう。

頭金を入れる?ローンを借りる?
新NISAのスタート以降、投資へのハードルが下がったからでしょうか、住宅ローンの考え方が変わってきています。低金利の住宅ローンを最大限に活用し、手元資金は積極的に資産運用に回すという考え方が注目されてるのです。
例えば、住宅ローンを金利1%で借りている場合、毎年1%の利息を支払う必要があります。一方、投資は、長期的な投資をすることで年率3〜5%程度のリターンが期待できると言われています。
次の例で試算してみますね。
(例)
50歳
住宅予算:3,500万円
定年の65歳以降にローンを残したくない
3,500万円を現金一括払いするか?
頭金2,000万円と借入1,500万円で支払うか?
1,500万円を金利1.0%、返済期間15年で借り入れた場合
ローンの利息116万円+ローン手数料33万円=合計149万円の負担が生じます。
※金利の変動は考慮しない
1,500万円を年3%で15年間運用した場合
資産運用の利益:837万円
こうしてみると頭金を入れるより借入をした方が有利になることがわかります。ただし、住宅ローンを利用して手元資金を運用する戦略は高いリターンを期待できる一方で当然ながらリスクも伴います。
★市場リスク
資産運用には元本割れのリスクがあります。株価や投資信託の価格が下落し、運用益が住宅ローンの金利を下回る可能性があります。
★金利上昇リスク
変動金利の場合、市場の状況によって金利が上昇する可能性があります。金利が上昇すれば、ローンの返済額が増え、運用益を上回るリスクが高まります。
ポイントは「住宅ローンの金利よりも高い年利で運用できているか?」1年に1度は運用成績を確認するようにしましょう。
資産運用は一定のリスクが伴います。元本割れや金利上昇などのリスクを十分に理解し、ご自身のライフプランやリスク許容度と照らし合わせて慎重に判断することが重要です。
まとめ
50代でも住宅ローンを組むことは可能です。
★借入期間に注意しましょう!
50代での住宅ローンは、若い世代に比べて借入期間が短くなります。月々の返済額が大きくなりがちなので、家計を圧迫しないかシミュレーションを重ねて確認してください。借入額と自己資金のバランスを慎重に考えることが重要になってきます。。
★団体信用生命保険(団信)を確認しましょう!
50代になれば、健康上の理由で団信に加入できない可能性も考えられます。団信に加入できないと、ローンを組めない金融機関が多いため、事前に確認が必要です。
★定年後の収入減に備えましょう!
多くの人が65歳前後で定年を迎え、収入が大きく減少します。定年後も住宅ローンの返済が続く場合は、公的年金や退職金を考慮した返済計画を立てましょう。
50代からの家づくりは、これからの人生をどう過ごしたいか?ご自身とご家族の未来を真剣に考える良い機会です。後悔のない家づくりのために、まずはご家族で将来についてじっくり話し合うことから始めてみてはいかがでしょうか。
「このまま話を進めて大丈夫かな…?」と少しでも不安を感じたら、どうぞお気軽に家づくり学校へご相談ください。お金のこと、家づくりの進め方、住宅性能のことまで、中立的な立場からわかりやすくお伝えします。