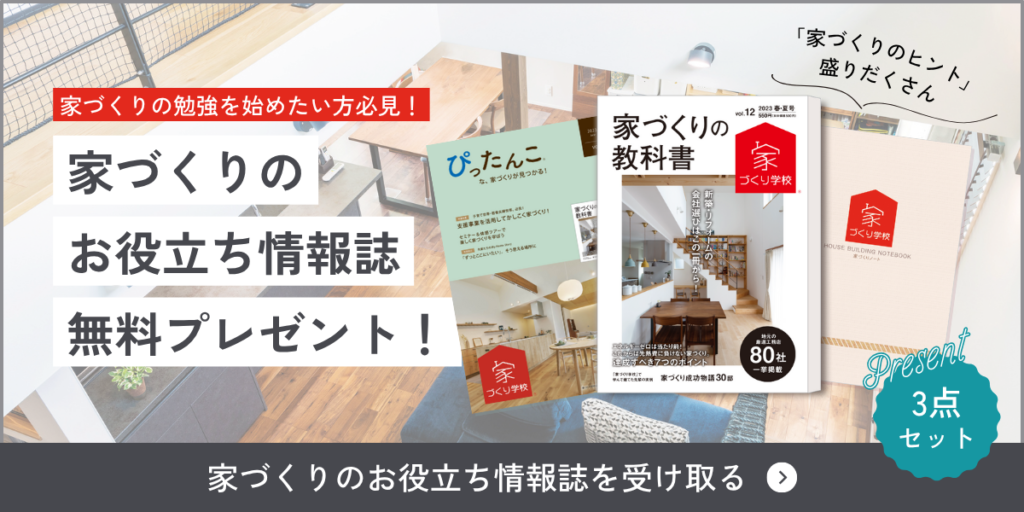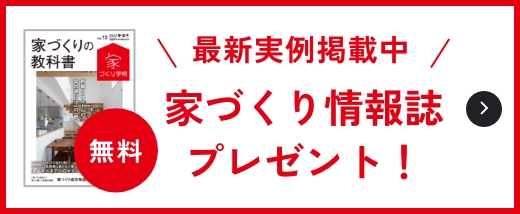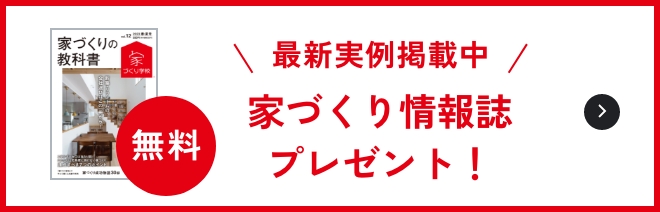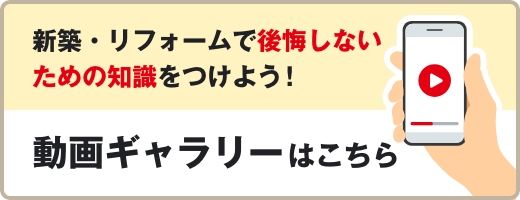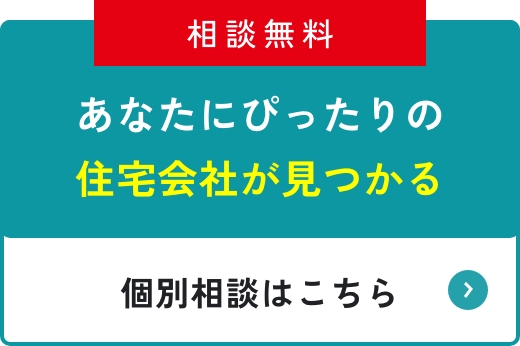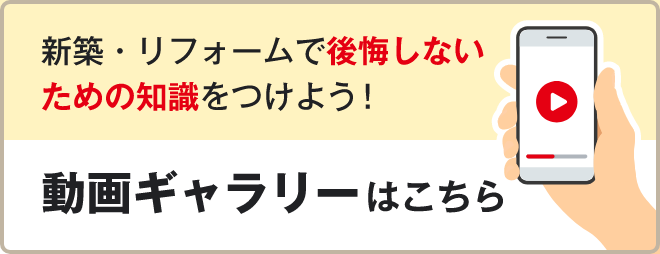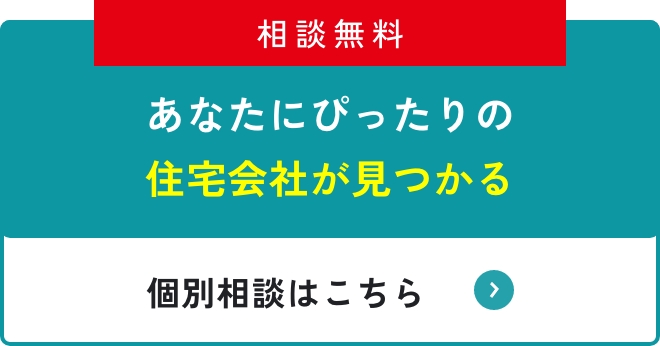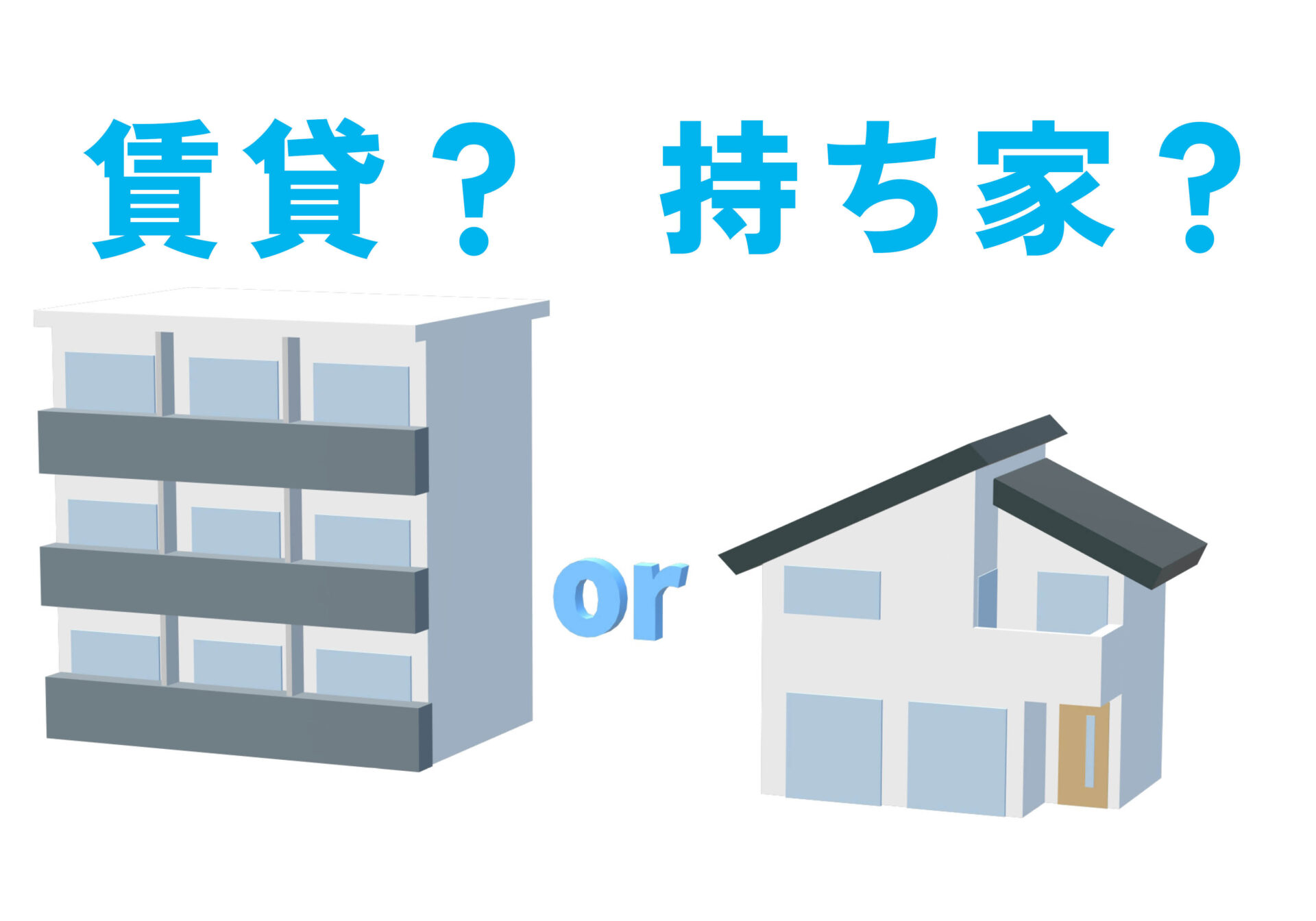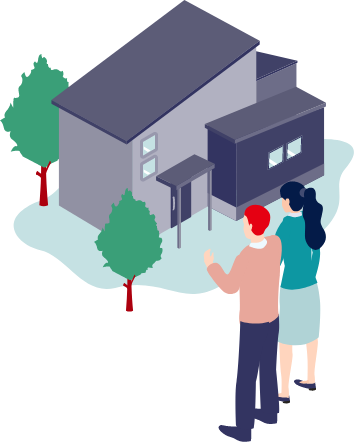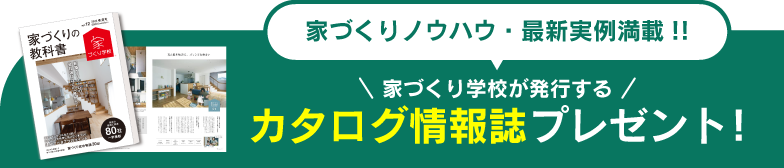注文住宅ってなんでこんなに高いの?|高くなる5つの理由と予算オーバーを防ぐ方法

「注文住宅って、どうしてこんなに高いんだろう?」見積もりを見て、思わずため息をついたことはありませんか?
建売住宅と比べると、注文住宅は数百万円単位で価格が上がることも珍しくありません。
「やっぱり贅沢だから?」「業者にぼったくられてる?」──そんな不安を抱く方も多いですが、実は高くなるには明確な理由があります。
本記事では、注文住宅が高くなってしまう理由から、予算オーバーを防ぐ具体的な対策までを丁寧に解説。「なぜ高いのか」を理解し、「どうすれば納得のいく価格で建てられるか」までを一気に学べます。
この記事でわかること
- 注文住宅が「高い」と感じる主な理由と、建売との費用差
- 予算オーバーが起こりやすい典型パターンと注意点
- 費用を抑えながら満足度を落とさない6つの工夫
この記事を監修した人

家づくり学校アドバイザー / 2級FP技能士・住宅ローンアドバイザー
今井 園美
子どもの教育資金で苦労した経験からファイナンシャルプランナーの資格を取得。家づくり学校ではアドバイザーとして家づくり全般のサポートをするのはもちろん、専門知識でお金や住宅ローンの悩みも解決している。
ムリのない予算が建てられる個別相談はこちら>>
1.注文住宅が「高すぎる」と感じるのはなぜ?
注文住宅の見積もりを初めて見たとき、「え、こんなにするの?」「ちょっと現実的じゃないかも…」──そう感じる方は少なくありません。
建売住宅や中古住宅の価格を見慣れていると、同じ“家”なのに注文住宅の方が割高に感じやすいもの。その原因は、注文住宅では価格の内訳が見えにくい構造になっているからです。
建売住宅の場合、土地・設計・建築・外構などをまとめて仕入れ・効率化しており、費用構造がシンプルでわかりやすい一方、注文住宅では「設計の自由度」「打ち合わせ回数」「仕様の選定」などの工程が、一人ひとりの要望に合わせて細分化されています。
関連記事>>注文住宅と建売住宅の違い
つまり、カスタマイズすればするほど、価格の仕組みが見えにくくなるのです。
次の章では、実際に建売住宅と注文住宅の費用相場を比較しながら、「どこで金額差が生まれるのか」を整理します。
2.注文住宅は本当に高い?費用相場を建売住宅と比較
まずは、建売住宅との費用差を具体的な数字で見てみましょう。
注文住宅と建売住宅の価格を比較
以下の表は、住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」の建売住宅と土地付注文住宅の全国平均金額のデータをもとに作成しています。
| 住宅面積 | 住宅の坪単価目安 | 金額(土地+建物) | |
| 建売住宅 | 100.7㎡(約30坪) | 60~80万円 | 3,826万円 |
| 土地付注文住宅 | 111.1㎡(約33坪) | 80~100万円 | 5,007万円 |
地域や仕様によって差がありますが、同じ規模でも注文住宅は500〜1,000万円ほど高くなるケースが一般的です。
この価格差の理由は、コスト構造と自由度の違いにあります。
建売住宅は大量仕入れ・標準仕様・同時施工によってコストを抑えていますが、注文住宅は1棟ごとに設計・発注・施工を行うため、その分コストが積み上がるのです。
自由設計がコストを押し上げる理由
注文住宅の大きな魅力の一つが「自由設計」。間取り、デザイン、素材、断熱性能、設備など、すべてを自分たちの理想に合わせて選べます。
しかし、その自由度こそがコストを上げる要因でもあります。
- 壁や屋根の形状が複雑になる
- 窓の数やサイズを増やす
- 造作家具や吹き抜けを採用する
このような仕様変更が加わるたびに、資材費や人件費が上昇します。
また、打ち合わせや設計変更が多いほど、設計士・現場監督・職人の稼働コストも増加します。「思い通りの家をつくれる」自由度の裏側には、人と時間のコストが存在するのです。
近年では住宅そのものの価格も上がっています。価格高騰については以下の記事で解説しています。
関連記事>>注文住宅の値上がりはいつまで続く?価格高騰時代の賢い家づくり
注文住宅は“高いけれどコスパが良い”場合も
一見すると高く見える注文住宅ですが、長期的なコストパフォーマンスで見ると話は変わります。
- 断熱性・気密性が高く、光熱費を抑えられる
- 耐震・耐久性に優れ、メンテナンス費用が少ない
- 間取りを将来設計できるため、リフォーム頻度が減る
こうした要素を含めて30年スパンで見れば、総支出では建売住宅と大差がない場合もあります。
また、家族のライフスタイルに合わせて間取りを最適化できるため、「住んでからの満足度」や「暮らしの快適性」は注文住宅の方が高くなる傾向があります。
家づくりは、初期費用だけでなく、光熱費をはじめとするランニングコストのことも踏まえて計画することが大切です。
3.注文住宅が高くなる5つの理由
注文住宅が高くなるのにはきちんとした理由があります。
「どこにお金がかかっているのか」を理解すれば、無駄を省きながら納得して家づくりを進めることができます。
- 住宅と土地を別で購入するケースが多い
- 打ち合わせや設計回数が多く、人件費がかさむ
- 住宅性能や設備グレードが高い
- オプションの選択肢が多く、追加してしまう
- 資材・人件費などの価格上昇
ここでは、代表的な5つの要因を順に見ていきましょう。
高い理由①:住宅と土地を別で購入するケースが多い
建売住宅は、土地と建物をセットで一括仕入れするため、コストが抑えられています。一方で注文住宅は、土地を個別に探して購入し、その上に家を建てるのが一般的です。
「土地探し→設計→建築」というプロセスが分離しているため、仲介手数料・登記費用・造成費など、土地取得に関するコストが別途発生します。
また、土地の条件(形状・地盤・方角)によっては、追加の地盤改良費や設計調整費が必要になる場合もあり、
結果として建売住宅よりも費用がかさむ傾向にあります。
高い理由②:打ち合わせや設計回数が多く、人件費がかさむ
注文住宅は「ゼロからつくる家」。理想を形にするために、設計士やコーディネーターとの打ち合わせが何度も行われます。
間取りの修正や仕様変更を重ねるたびに、設計担当者・施工管理者・現場職人など、多くの人の手間と時間がかかるのです。この人件費・工期コストが積み重なり、結果として総額が高くなります。
高い理由③:住宅性能や設備グレードが高い
最近の注文住宅では、高気密・高断熱・耐震等級3・ZEH対応といった高性能仕様が主流になっています。これらは長期的に見れば光熱費や維持費を抑えられる優れた性能ですが、初期費用としてはどうしてもコストが上がります。
また、キッチン・浴室・窓・外壁材などの設備グレードを上げる選択肢も多く、“せっかく建てるなら良いものを”と選んでいくうちに、一つ一つの積み上げが全体コストを押し上げてしまうのです。
高い理由④:オプションの選択肢が多く、追加してしまう
注文住宅では、標準仕様に加えてさまざまなオプションが用意されています。たとえば、造作収納・間接照明・タイル張り・外構デザイン・太陽光発電など。
打ち合わせの中で「せっかくだから」と追加していくうちに、最初の見積もりより数百万円アップするケースも珍しくありません。オプションは満足度を高める反面、コスト管理を難しくする“落とし穴”でもあるのです。
見積もりの段階で「どこまでが標準仕様か」を明確にし、オプションをリスト化しておくことが、後悔しないコツです。
高い理由⑤:材料や設備を個別に選ぶため割高になりやすい
注文住宅では、無垢材のフローリングやデザイン性の高いキッチン、暖房機能付きの浴室など、施主の希望に応じて自由に仕様を選べます。しかし、こだわりが増えるほど高グレードの建材や設備を使うことになり、その分材料費は上がっていきます。
さらに、建売住宅のように同じ建物を大量につくるわけではないため、一括仕入れによるコストダウンが働きません。注文住宅は一軒ごとにオーダーが異なるため、材料の発注数は少量になり、仕入れ価格が割高になる傾向があります。
つまり、「こだわりによる高仕様」+「大量仕入れができない構造」この2つが重なることで、注文住宅では材料費が高くなりやすいのです。
4.見積もりが予算オーバーになる典型パターン
注文住宅では、契約前に立てた予算や見積もりから、最終的な費用が上回ってしまうケースが少なくありません。
- 契約後に仕様変更が発生する
- オプションの積み重ねで上限突破
- 土地条件や地盤改良で追加費用が発生
- 諸費用・税金・外構を予算に入れていない
ここでは、特に予算を押し上げやすい代表的な4つのパターンを紹介します。
契約後に仕様変更が発生する
契約時の見積もりは、まだ仮のプランや標準仕様で作られることがほとんどです。
打ち合わせが進むにつれて「収納を増やしたい」「窓を大きくしたい」「和室を追加したい」などの仕様変更が発生すると、その都度費用が加算されていきます。
特に、建築確認申請後の変更は、設計費だけでなく材料費や工事費も見直しが必要となり、1回の変更で数十万円〜100万円以上増えるケースもあります。
オプションの積み重ねで上限突破
注文住宅では、標準仕様以外に多くのオプションが用意されています。例としては、以下のようなものがあります。
- 造作の洗面台や収納家具
- 吹き抜け・勾配天井・間接照明
- 無垢材フローリングやタイル壁などの内装
- 外構・庭・カーポート・ウッドデッキ
ひとつひとつの金額は小さく見えても、合計すると100万〜300万円ほど上乗せされることも珍しくありません。「せっかくだから」という気持ちが重なることで、いつの間にか予算を超えてしまいます。
土地条件や地盤改良で追加費用が発生
土地を購入した時点ではわかりにくいものの、建築を始めてから費用が増えるケースもあります。代表的なのは以下のような追加費用です。
| 内容 | 追加費用の目安 |
| 地盤が弱く、地盤改良工事が必要 | 30〜100万円 |
| 高低差や変形地で擁壁・造成工事が必要 | 50〜200万円 |
| 水道・ガス・排水などの引き込み工事 | 10〜50万円 |
こうした費用は土地の価格には含まれておらず、見積もり外として追加されるケースが多いため、「土地は安く買えたのに、総額では高くついた」という事態につながります。
諸費用・税金・外構を予算に入れていない
建物本体の価格だけを基準に予算を組んでしまい、その他にかかる費用を見落としやすいケースもあります。実際、家づくりには次のような費用が必要です。
- 登記費用・住宅ローンの手続き費用(司法書士報酬・事務手数料など)
- 火災保険・地震保険などの保険料
- 外構工事費(駐車場・フェンス・門柱・庭など)
- 引っ越し費用や家電・家具の購入費
これらは建物価格とは別枠で必要になるため、最初の見積もりに含まれておらず、後になって予算を圧迫する要因になります。
5.予算オーバーを防ぐ6つの具体策
注文住宅の費用は家づくりの進め方や選択の積み重ねによって大きく変わります。
ここからは、予算が膨らみやすいポイントを踏まえたうえで、実際に有効な具体的な対策を6つご紹介します。
- 優先順位を明確にする
- 土地価格を抑える工夫をする
- シンプルな形状・コンパクト設計にする
- 延床面積を落とす
- 設備グレード・オプションを見直す
- 複数社見積もり+資金計画の見直しを行う
しっかり押さえておけば、「気づいたら予算を超えていた」という事態を防ぎやすくなります。
①優先順位を明確にする
すべての希望を叶えようとすると、必ず予算オーバーになります。まずは「絶対に実現したいこと」「妥協してもよいもの」を整理しましょう。
例:優先順位の決め方
・【優先】性能・耐震性・断熱性など生活の安心に関わるもの
・【できれば】キッチンの仕様、床材の材質、造作家具など
・【削りやすい】装飾的な照明、過剰な収納、庭のデザインなど
最初に優先順位を決めておくことで、打ち合わせ後半での“感情優先の追加”を防ぐことができます。
②土地価格を抑える工夫をする
土地の価格は、建物と同じくらい予算を左右します。以下の視点で土地選びの見直しができると、総予算を抑えやすくなります。
例:土地価格を抑える工夫
・最寄り駅からの距離を妥協する
・旗竿地・変形地でも使いやすいプランを検討する
・造成費・地盤改良費がかかる土地を避ける
「安い土地=悪い土地」ではなく、“建て方次第でコストバランスを最適化できる土地”を探す視点が重要です。
③シンプルな形状・コンパクト設計にする
土地の選び方だけでなく、「家そのものの形」もコストに直結します。
特に注文住宅では、デザインや間取りにこだわるほど構造が複雑になり、建築費は上がってしまいます。だからこそ、家の形状をシンプルにすることは、費用を抑えるうえで効果的な方法のひとつです。
建物価格の落とし方のポイント
・凹凸・L字型・複雑な屋根は施工費が高くなる
・吹き抜けやスキップフロアも構造材・工事工数が増える
・正方形・長方形のシンプルな形が最もコスト効率が良い
形状をシンプルにすることは、見た目だけでなく「施工のしやすさ」=「工事費の節約」に直結します。
④延床面積を落とす
延床面積(家全体の広さ)は、建築費に直結する最もシンプルな数値です。面積を数平方メートル減らすだけでも、建材・人件費・設備のすべてを抑えることができます。
面積を抑えながら暮らしやすさを維持するためには、「回遊性の高い間取り」「収納の位置とサイズの最適化」「吹き抜けや中庭で“狭さを感じさせない工夫”」など、「小さくて快適な家」の設計視点が重要になります。
⑤設備グレード・オプションを見直す
こだわりが増えるほど、設備や内装のグレードは上がっていきます。しかし、すべてを高級仕様にする必要はありません。
見直しやすいポイント例
・トイレ・洗面台は標準仕様+収納追加で十分な場合も
・無垢床ではなく突板・高耐久フローリングという選択肢もある
・造作家具より既製品+カスタムのほうが費用が抑えられる場合も
“すべてを妥協せず、こだわる場所だけに集中する”のが費用を抑えるコツです。
⑥複数社見積もり+資金計画の見直しを行う
1社だけの見積もりでは、費用の妥当性が判断できません。
複数社見積もりのメリット
・工事費・設計費の相場感がつかめる
・仕様変更の優先順位が整理できる
・無駄なオプションや重複費用が見えてくる
また、資金計画(住宅ローン・自己資金・補助金)の見直しを行うことで、「予算に合わせて無理やり削る」のではなく、「予算自体を再調整する」という選択肢も取れるようになります。
ここまで読んで「自分の理想と予算のバランス、本当に大丈夫かな…」と感じた方も多いかもしれません。そんなときは、ひとりで抱え込まずに第三者のプロに相談するのもひとつの方法です。
「家づくり学校」では、複数の住宅会社の見積もり比較や予算の相談を無料で行っています。
「ムリのない予算内で建てられるのか知りたい」「どこから削ればいいのか判断できない」そんな方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
6.「注文住宅 高い」に関するよくある質問
ここでは、注文住宅が高いと感じる方から寄せられるよくある質問をご紹介します。
Q1.注文住宅はなぜ高いと言われるのですか?
注文住宅は、土地と建物を別々に購入し、設計・仕様・設備を一から選ぶため、建売より工程や人件費が多く発生するのが理由です。さらに一棟ごとにオーダーメイドで建てるため、建売住宅のような大量仕入れによるコスト削減が難しく、結果的に単価が高くなりやすい構造になっています。
Q2.坪単価はいくらくらいが相場ですか?
全国平均では、建売住宅が60〜80万円/坪前後、注文住宅は80〜100万円/坪前後が目安です。
ただし、選ぶ住宅会社・設備・地域・土地条件によって大きく異なるため、坪単価だけで比較するのではなく、「総額+含まれている内容」で判断することが大切です。
Q3.どこを削れば費用を抑えられますか?
削りやすいポイントは「面積」「形状」「設備・素材」の3つです。
- 延床面積を少し小さくする
- 凸凹の少ないシンプルな形状の家にする
- キッチン・床材・造作家具などのグレードを見直す
逆に、耐震・断熱・構造など、暮らしの安全性に関わる部分はむやみに削らないほうがよい部分です。
Q4. 見積もりが予算を超えたらどうすればいいですか?
まずは、削れる部分と削ってはいけない部分を整理することが優先です。以下の流れで見直すと判断しやすくなります。
- 優先順位の低いオプション・設備から見直す
- 間取りや面積(延床面積・部屋数など)を再調整する
- 複数社の見積もりを比較し、価格や仕様の違いを確認する
不安な場合は、第三者の立場でアドバイスしてくれる「家づくり学校」などに相談するのも有効です。
7.まとめ
注文住宅が高く感じるのは、費用の構造そのものが建売住宅と大きく違うからです。
土地探し・自由設計・高性能仕様・オプション・小ロット発注など、さまざまな要素が積み重なることで、結果的に建売より費用が高くなりやすい仕組みになっています。
ただし、それは無駄にお金を払っているという意味ではありません。性能や耐久性、暮らしやすさ、家族のライフスタイルに合った設計など、長く住むほどに価値が感じられる“投資型の住まい”でもあります。
一方で、計画の進め方によっては、想定していた費用より数百万円オーバーしてしまうケースも少なくありません。これを防ぐためには、次のポイントを押さえておくことが大切です。
- 注文住宅が高いのは「土地と建物の分離・自由設計・人件費・材料単価」など構造的な理由によるもの
- 仕様変更・オプション追加・地盤改良・諸費用の見落としが、予算オーバーの主な要因
- 優先順位の整理・土地と建物のバランス・延床面積調整・設備グレードの見直しが効果的な対策
- 複数社の見積もりや第三者への相談によって、最適な判断がしやすくなる
家づくりは、正解が1つではない選択の連続です。「高いから無理」と諦めるのではなく、仕組みを知り、優先順位を整理し、必要な部分に予算を掛けることで、予算内でも“納得できる家づくり”は十分に可能です。
もし今、「何から決めればいいかわからない」「この予算で建てられるのか不安」と感じているなら、一度プロに相談してみるのも立派な前進です。
次のステップに進むための個別相談や無料サポートを活用しながら、理想の家づくりを現実のものにしていきましょう。
家づくりの初心者はまず家を建てる流れを抑えよう!
家を建てる流れや手順を10ステップで徹底解説!必要な期間や費用相場も紹介