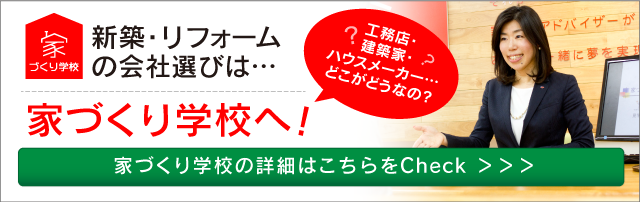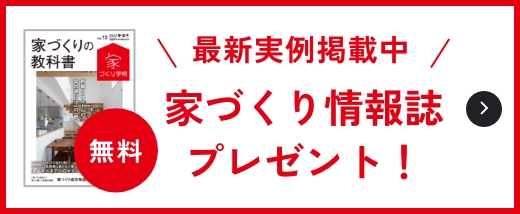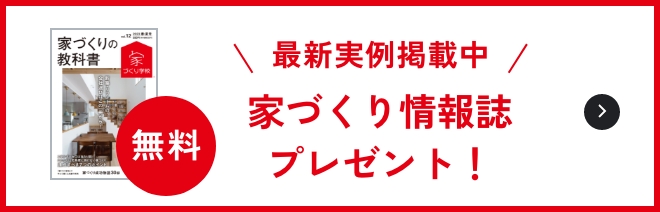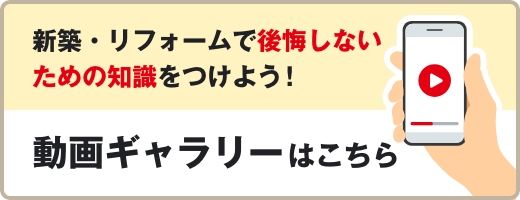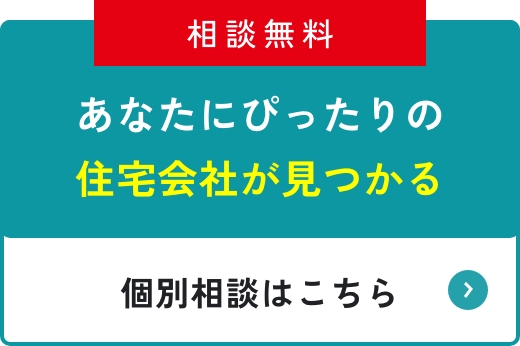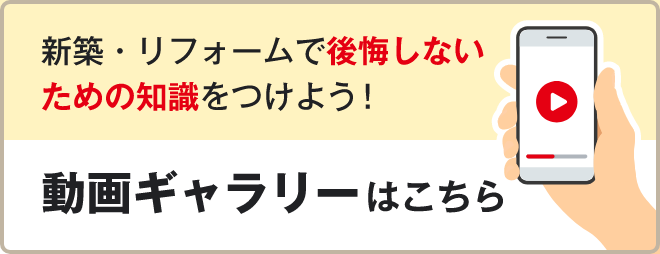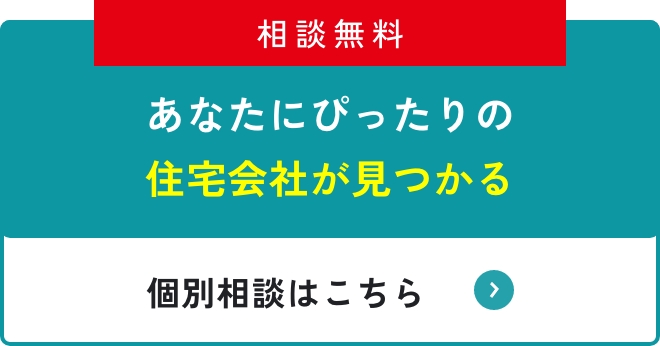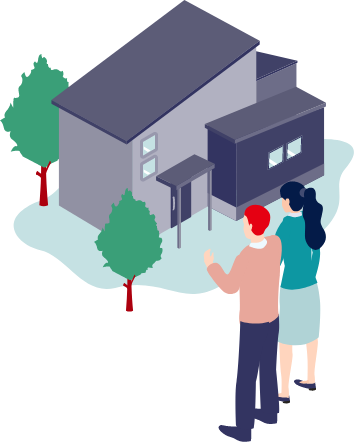失敗しない工務店の選び方とは?良い工務店・悪い工務店の見分け方を解説
2023.11.24
2023.09.19

家づくり成功のカギは住宅会社選びにあるといっても過言ではありません。
住宅会社と言っても、ハウスメーカーからビルダー、地元工務店、設計事務所などさまざまな業態があります。
中でも「工務店」はとても数が多く、自分たちにあった会社を見極めるのは非常に困難です。
そこで今回は「失敗しない工務店の選び方」をテーマに、見極め方や見るべきポイント、注意点などを解説します。
本記事は、累計23000組以上の家づくりをサポートさせていただいた「家づくり学校」が執筆しています。
家づくり学校では、家づくりの基本的な知識や予算設定のコツ、信頼できる住宅会社・工務店の見極め方などを公平かつ中立の立場で個別相談やセミナーを通してレクチャーしています。
また、個別相談はオンラインでも承っております。
ご利用はいずれも無料ですので、注文住宅を建てることをご検討中の方は、ぜひ一度ご相談くださいませ。
\あなたにぴったりの住宅会社をご紹介!/
オンライン個別相談も好評受付中!
この記事を読んでいただきたい人
- 工務店かハウスメーカーのどちらに依頼をすればよいか悩んでいる人
- 家づくりを何から始めるべきか分からず困っている人
- 自分たちに合う住宅会社が分からない人
- 住宅会社をいろいろ見過ぎて分からなくなった人
1.ハウスメーカーより工務店がおすすめ?工務店とハウスメーカーの5つの違いを解説
注文住宅を建てる場合には、工務店やハウスメーカーなど、さまざまな依頼先の選択肢があります。
本章では、工務店とハウスメーカーの違いや工務店ができる家づくりについて解説します。
工務店の数はとても多く、地域によっては1000社以上あると言われています。
工務店によって得意分野や特徴はさまざまです。本記事を参考に理想の家づくりを進めましょう。
そもそも工務店とは?ハウスメーカーとの違い
工務店は住宅の建築依頼先の1つです。
基本的にハウスメーカーよりも狭い施工エリアで住宅工事を請け負い、新築やリフォーム、増築なども含む住宅工事を進めていくのが工務店の役割です。
工務店というと小規模で無名というイメージがまず頭に浮かぶかもしれませんが、中には中堅ビルダーのような工務店もあり、施工エリアが広く、近隣の県や市に支店や営業所を設置しているタイプの会社もあります。
また、フランチャイズに加盟している工務店や、全国的に「良いものづくりをする会社」として有名な工務店もあります。
ハウスメーカーは自社ブランドを持って、全国規模で営業展開している住宅会社のことです。対応エリアが広く、各地域に展示場(モデルハウス)をはじめとする営業拠点があります。
以下でハウスメーカーとの大きな違いについて解説します。
工務店とハウスメーカーの違い①:費用・コスト
基本的には工務店の方がコストは安く済みます。
ハウスメーカーの長所や強みは、建材や規格の共通化・大量生産によって原価を抑えられる点です。
しかし、その一方で工務店よりも莫大な広告費や人件費、展示場などの維持費をかけています。建築には直接関係しないこれらの費用がある分、工務店の方が安く、適正な価格で建築が可能であると言えます。
工務店とハウスメーカーの違い②:施工エリア
施工エリアが広いのはハウスメーカーです。全国各地に営業所を構えているので、基本的にどの地域でも対応が可能です。
工務店の施工エリアは市町村や県内に限定されている場合がほとんどで、工務店の中でも比較的規模が大きい中堅ビルダーであっても地域密着色が強く、支店や営業所が設置されている範囲も近隣の県や市にとどまります。
ただしその分、工務店のスタッフの方が施工エリアのことに精通しており、地域の実情や周辺環境も詳細に理解しています。地元のスタッフならではの土地勘や気候風土を活かした家づくりを提案できる可能性が高いと言えます。
工務店とハウスメーカーの違い③:プランの自由度
間取りなどのプランの自由度は工務店の方が高いです。
ハウスメーカーで家を建てる場合、注文住宅といえども規格化されていることが多く、あらかじめ用意されたプラン・建材・設備から好きなものを選び、組み合わせるのが一般的です。デザイン・間取りの自由度は低めで、規格外の注文住宅を建てると割高になる場合もあります。
一方、工務店の場合は、自由にプランを考えられます。自分たちの思い通りにこだわった家づくりを目指すのであれば、自由な設計対応ができる工務店に頼む方がいいでしょう。
ただし、工務店ごとに得意なデザインや工法は大きく異なるので、事前にどのような家づくりにしたいかを決めてから会社を訪問するようにしましょう。
工務店とハウスメーカーの違い④:工期の長さ
工期はハウスメーカーの方が短く済むケースが多いです。ハウスメーカーは建築資材の調達から施工までの流れがシステム化されており、効率的に進めることができます。
一方、工務店では現場で資材の加工をするところから始まります。工期は住宅の規模や施工時期、プランなどによっても大きく変わってきます。
工務店とハウスメーカーの違い⑤:施工精度
施工精度については、どちらが高いとは一概には言えません。
ハウスメーカーの方がプランや建材を規格化・共通化している分、品質が均一になると言えます。
一方、工務店の場合は職人の腕によって大きな違いが出るので、施工精度は一定とは言えないのが現状です。工務店に依頼する際には、情報収集を念入りに行い、建築現場を見学したり利用者の評判なども聞いたりして、大工の腕をはじめとする工務店の施工力をチェックしておいた方がいいでしょう。
家づくり学校ではぴったりの住宅会社をご紹介!
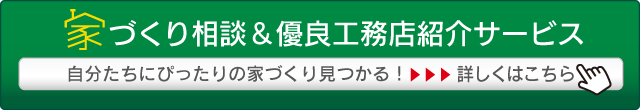
「自分にあった住宅会社が分からない」という方は「家づくり学校」で家づくりの基本知識を身につけ、住宅会社の見極め方を学ぶのがおすすめです。
全国選りすぐりの住宅会社の中から、あなたにぴったりの住宅会社を紹介・提案いたします。知識をつけた上で選ぶので、納得の家づくりができます。
2.注文住宅を工務店で建てる4つのメリット
本章では工務店で建てる4つのメリットを解説します。
①価格を抑えて家を建てることができる
工務店は必要最小限の人数で回しており、専属の営業担当がいないことが多いです。
また、大々的に広告費をかけることもないので、人件費や広告費など建築には直接関係しない費用が発生しにくい分、適正な価格で家を建てることができます。
②プランが豊富で融通がききやすい
工務店の家づくりは規格化されていないことが多く、プランに自由度があることが強みです。建築中の急なプラン変更も臨機応変に受け入れてくれる場合もあります。
③何かあったときに迅速に駆けつけてくれる
小規模な会社だからこそ小回りがきき、何かあればすぐに駆けつけてくれます。地域に根付いている工務店が多いので柔軟な対応が可能になります。
④高性能な住宅を建てることができる
工務店の中には高い水準の住宅性能で家づくりを行う会社があります。
高断熱・高気密・高耐震でパッシブデザインなどを駆使し、快適性や省エネ性を実現できる工務店は「スーパー工務店」と呼ばれます。
スーパー工務店については『住宅会社の見極め術』: 5章「スーパー工務店」という選択をご覧ください。
ただし、このような高水準な家づくりができる工務店は全体の約1割。全ての工務店が高水準な家づくりができるとは限りません。ですから、工務店に依頼する際は、会社を見極める目を持つことがとても大切なのです。
「家づくり学校」では家づくりの基本知識を習得していただいた上で、ご予算・要望に合った住宅会社をご提案しています。
ご利用は何度でも無料。ぜひこれからの家づくりにお役立てください。
3.優良工務店の選び方、見分け方
本章では優良工務店の失敗しない選び方を解説します。
工務店で建てる際のメリットやデメリットを踏まえて、失敗しない家づくりにお役立てください。
失敗例から学ぶ工務店を選ぶ時の注意点とデメリット
工務店によって施工精度や工期にムラがある
施工精度や職人のレベルは工務店によって大きくばらつきがあります。技術面の判断は素人目には難しいところがありますが、分かりやすいところでは断熱・気密性能がどれくらいなのかを事前に確認するようにしましょう。
また、工期も小規模ゆえに大手ハウスメーカーと違って遅れてしまうこともあります。工務店に依頼する際は、期間に関してもしっかり打ち合わせするようにしましょう。
具体的な家の仕上がりがイメージしづらい
工務店はモデルハウスや展示場を持っていないことが多いので、実際にどんな家になるのかイメージがしづらいです。
モデルハウスを持っていなくても、完成見学会やOB邸訪問などの見学イベントは行っていることが多いので、気になる工務店があれば積極的に参加しましょう。
提案力が弱い場合がある
工務店はハウスメーカーと違い「専属の営業」という立ち位置のスタッフがいない場合が多いです。そのため、しつこい営業などはあまりないですが、一方で提案力が弱いことがあります。
工務店の担当者にはどういう家にしたいか自分からしっかりと要望を出していく姿勢も大切です。
失敗しない工務店の選び方
では、工務店で建てる際、具体的にどんなことに気を付ければいいでしょうか?
以下で失敗しない工務店の選び方を、5つのポイントに分けて解説します。
①会社の経営状況を確認する
会社として安心して任せることができるか、経営状況を確認しておくことはとても大切です。
経営状況を確認する一つの指標として「年間施工棟数」が挙げられます。施工棟数は経営状況を全て表しているわけではないですが、工務店の場合、年間10棟以上の新築を建てていると、比較的、安定経営と言えます。
工務店が倒産してしまうと、アフターメンテナンスに影響するので重要なポイントです。
②複数社に相見積もりを取る
工務店に限ったことではないですが、依頼先の意思決定をする際には複数社で見積もりをしましょう。なぜなら、1社だけの建物プラン・見積もりを見ても、その会社が本当に自分たちに合っているかどうかが分からないからです。
同じ土地、同条件で2~3社に見積もりやプランを出してもらえば、価格やプラン提案力を比較することができるので、納得のいく決断をすることができます。
③自社施工の工務店を選ぶ(施工を丸投げにしない工務店を選ぶ)
工務店の中には、施工は全て下請けに丸投げ…という会社もあります。下請け業者に頼むことで余計な費用が追加されたり、どちらが責任を持つかで揉める原因にもなります。
そういったトラブルを避け、安心して家づくりを任せるためにも、判断基準として自社施工であるかどうかは大切なポイントです。
④特徴や価格を調べて自分たちに合った工務店に依頼する
デザイン性を重視する、自然素材をふんだんに使用する、住宅性能にこだわる、など、工務店ごとに特徴は異なります。また、工務店ごとに価格も大きく異なります。
自分たちがどんな家づくりをしたいか、予算はどこまでかけられるのかを整理して、検討すべき工務店を選びましょう。
⑤円滑なコミュニケーションがとれるか
家づくりで大切なことは多々ありますが、担当者としっかりとコミュニケーションが取れるかどうかはとても大事な要素です。担当者とコミュニケーションが取れないと、現場に要望が正しく反映されないからです。
しっかりとしたコミュニケーションがとれることで、その都度意見を言いやすくなり、良い関係を築くことができます。
自社の意見を押し付けてきているだけになっていないか、こちらの意見を鵜呑みにするだけになっていないかなども注意してみましょう。
4.工務店に依頼した後の注文住宅ができるまでの流れ
家づくりのプランが決まり、工務店と契約をしたら、着工になります。
家が完成するまで何をしたらいいのか、注文住宅が完成するまでの大まかな流れと注意点を解説します。
本章では、近所へのあいさつ回りや地鎮祭・上棟式などのイベントまでご紹介します。
注文住宅完成までの流れ
一般的に着工(工事の開始日)~竣工(工事が完了して建物が完成する)は、通常およそ4~6カ月程度かかります。
以下で具体的な流れをご紹介します。
①近所へあいさつ回り
建築中は工事の音や資材の搬入などで近隣に迷惑をかけることもあるので、事前にあいさつ回りをしておくことが大切です。タイミングは着工前と地鎮祭の時に行くのが一般的です。工事のスケジュールが決まったタイミングでも構いません。
あいさつ回りをすることで入居後の安心した生活にもつながります。事前に顔見知りになってから新生活を始めることで、自然災害などいざという時には助け合える関係も築きやすいです。
②地鎮祭
地鎮祭とは、新しい建物を建設する前に行う、土地を守る神様に工事の安全を祈願する儀式のことです。地鎮祭の手配は施工会社に任せたり、施主自ら近くの神社の神主さんに依頼したりするなどさまざまです。
費用は神主さんへの謝礼として渡す「初穂料」で2~5万円程度です。初穂料とは、もともと稲作の実りに感謝して神様にお供え物のことで、その名残から今でも神様へのお礼のために支払うお金のことを意味しています。
その他にも「奉献酒」と呼ばれる日本酒をお供えする必要があり、奉献酒にかかる費用の目安は5,000円程度です。
地鎮祭を行うかどうかは、施主が判断する立場にあります。地鎮祭の準備は基本的には施工会社が進めてくれますが、行いたくない場合はその旨を施工会社に依頼して行わずに建築工事を始めることも可能です。
③着工
地鎮祭が終わるといよいよ着工です。
家の工事が始まったら、進捗状況を確認しましょう。1~2週に1回と期間で確認の日を決めておくか、頻繁に行けない場合は、「基礎工事・木工事(構造)」「断熱施工工事」「内装工事」「住宅設備の設置」など、工程ごとに確認するのも一つの方法です。
実際に建築現場を見ることで、工事の内容に疑問や当初予定していたことと違う、など問題がある場合は、依頼先の住宅会社の担当者や現場監督に確認するようにしましょう。
★工務店への工事代金の支払い
注文住宅は工事代金を複数回支払うのが一般的です。(下記①~④を参照)
支払時期や金額を確認して、自己資金が不足する場合は分割や住宅ローンのつなぎ融資などを検討しましょう。
①契約時:工事費の10%程度を支払う。着手金は、自己資金で支払う必要がある
②着工時:工事費の20%程度を支払う。
③中間(上棟)時:工事費の約30%程度を支払う。
④引渡し時:残代金を支払う。
④上棟式
上棟式とは、柱や梁などの骨組みが完成して屋根がかかった段階で、工事関係者が集まって、最後まで工事の安全を祈る儀式のことで、棟上げ式とも呼ばれます。
上棟式の想定される予算は、式の内容や参加人数によっても変わってきますが、約10万円程度です。
⑤完成・引き渡し
建物が完成したら、竣工検査を受けて引き渡しになります。入居まで1~2週間です。
竣工検査時の具体的なチェックポイント
「竣工検査」とは、建物が完成した後、外構も含めて施工状態に不具合がないかを確認するための検査のことです。
以下、竣工検査時に見るべき具体的なチェックポイントです。
- 床や壁にへこみがないか(歩いていると「キュッ」と床鳴りする場合もあります。耳でもチェックしましょう。)
- クロスの端が剝がれていないか
- ドアや窓の開閉はスムーズか(窓はスムーズに動いても、雨戸や網戸が閉まりにくいというケースもあります。)
- コンセントの位置は適切か
- 水圧に問題はないか
- きちんと排水ができているか
- 水漏れ・ガス漏れはないか
- 外壁や洗面台のつなぎ目をコーキング材で隙間なく埋めているか
- 電気が各所に通っているか
- 鍵つきのドアなど、指定通りにせこうされているか
- 床の素材が切り替わる部分に段差がないか
5.工務店選びは家づくりの知識を付けてから!
家づくりでは、自分たちの予算にハウスメーカーや工務店と契約して住宅ローンの支払いに苦しんでしまう人や、希望のデザイン・間取り・性能を実現できず後悔する人が多くいます。
そんな失敗や後悔を少しでも減らすために、まずは家づくりについてしっかりと学び、自分たちに本当に合う住宅会社を選びましょう。
まずは「家づくりの基準」をつくる
「家づくり」はほとんどの方にとって初めての経験だと思います。経験がないことに対して最善の判断をしようとしても、自分たちの中に“基準”がなければできません。
家づくりの後悔の多くは、自分たちの無理のない予算はいくらで、どういう生活 がしたいのかといった要望や方向性が具体的にないまま会社を決めてしまったことに原因があります。
だからこそ「家づくり学校」では、個別相談や各種セミナーでの学びと、気になる住宅会社への見学訪問などの体感を通してあなただけの「家づくりの基準」をつくるお手伝いをさせていただいています。
ご利用は何度でも無料です。上手にご活用くださいませ。
6.まとめ
いかがでしたか。
本記事では『失敗しない工務店の選び方とは?良い工務店・悪い工務店の見分け方を解説』と題して、「ハウスメーカーと工務店の違い」や「工務店で建てるメリット」、「優良工務店の見分け方」「注文住宅ができるまでの流れ」について解説しました。
家づくり学校では選りすぐりの厳選工務店の中から、あなたにぴったりの住宅会社をご提案・紹介しています。
個別相談や各種セミナーを通して、知識を付けて賢く家づくりをしてください。